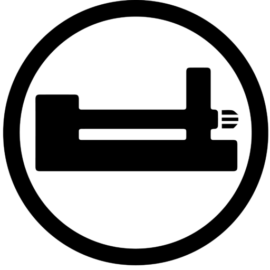小菅村でウッドマイザーによる小規模製材にトライ!
10月1日に実施したOPEN FOREST Kosuge 小規模製材講習。 大工、建築家、木工職人、林業、薪製造、フォレストアドベンチャー、土中環境と森林や木材との関わりを生業とする多様な仲間たちと共に体験したウッドマイザーによる製材WS。
10月1日に実施したOPEN FOREST Kosuge 小規模製材講習。
今回の目的は、小菅の湯・薪ボイラーへ供給する薪を製造している木の駅こすげ(北都留森林組合小菅事業所)の敷地内に保管されていた小規模製材機ウッドマイザーを再稼働させ、村民が木材をエネルギーだけでなく、マテリアルとしても活用できる道筋を確保し、木材の付加価値を高めること。






ウッドマイザーの稼働により、板材・柱材を取得した後に残る背板は薪ボイラー用燃料となり、ウッドマイザーの稼働率が高まれば高まるほど背板の発生量も増加し、薪も同時に確保できる体制の構築を目指している。
講師に大工棟梁である株式会社藤本工務店代表の藤本嶺さん、建築家でOffice of Teramoto代表の寺本健一氏さんをお招きして開催。当日は村長や、(株)源、(株)つくる座、NPO多摩源流小菅も参加頂き、とても充実したWSになった。皆さん、ご協力ありがとうございました。

WSは、午前に藤本さんの講義「木材を100%使い尽くす技術とは。」からスタート。その後、「木取りの仕方と製材のコツ。ウッドマイザー操作実演」を行い、午後から「ウッドマイザー製材体験」。実際に板材を挽き、ベンチを製作。1時間弱で立派なベンチが2セット完成し、自分も木材がこうして新たなマテリアルに生まれ変わる姿に衝撃を受けた。その後は、「ENTENKA焚き火セッション」。コーディネートを寺本さんにお願いさせて頂き、小菅村で地域材の付加価値を高めるための方法論について協議。つくる座代表の建築家・和田さんにもご参加頂き、川上は林業・森林ボランティア・土中環境整備チーム、川中は薪製造チーム、川下では村内の建築家、村外の建築家と木工製作チーム、そして大工が一堂に介して木材の活用を議論する機会は貴重だった。
当日の様子は、つくる座の酒井くんに撮影・編集を依頼させて頂き、素晴らしい仕上がりに。本当にありがとう!2部構成で編集してくれたので、記事後半に掲載。




ユーザーに最も近い場所で木材を扱う大工さんからの意見は画期的で、山側が持つA材〜D材という区分や品質に関する常識が、実は自由な活用をかなり拘束していることが認識できたことはとても有意義な学びとなった。
低質材と思われている木でも、挽けば優良な板材が取れることを実際に目撃すると、今までの常識だけが全てではないことが体感として獲得出来る。身体感覚を通じて物事を把握することで、向き合っている事象が、まさに「腑に落ちる」。一度、身体に落とし込まれると、思考だけでは拡大できない領域にアクセスできるような気がしてくる。とはいえ、製材についてはまだまだこれから学んでいくことも多い。






板材・柱材の村内外での利用・販売は、現在、関係者の皆さんと協議中。
WS以後、現在、村民有志がウッドマイザーの取り扱い方法の学習も含め、製材を定期的に実施している。Open Forestでは、手始めにMTB用のパンプトラック、バンク用の部材として、間伐材を挽く取り組みが今週からスタートする。今後も関係者と協力して、利活用や出口対策を考えていきたい。
舩木村長も自ら製材を行い、とても楽しそう。こうして一緒に参加頂けることが嬉しい。
また、地域の製材所との協力関係も構築したいところ。粗挽きした後のプレナ処理や細かい裁断は製材所と連携した方が効率が良いかもしれない。地域の製材所が減少する中(小菅村は1ヶ所のみ)、加工施設として重要な拠点である製材所を存続していくためにも、引き続き、小菅村ならではの木材流通の仕組みを考えていきたい。






最後に薪ボイラーの稼働状況について。ボイラーは順調に稼働しており、着実に灯油から薪への燃料代替が進んでいる。薪の含水率やボイラーの調整を丁寧に行っている小菅の湯・村上さんや、薪製造を担っている(株)源のスタッフの方々に感謝。






では、薪を使うことで、どれくらいコストメリットがあるのか?
木の駅こすげでは、1m3の薪材(主にスギ、ヒノキの間伐材)を5,000円/m3で買取を実施しており、薪の含水率を30%(ウェットベース)、カロリーを2,561kcal/kgとした場合、1m3の重量は約500kgになることから、薪1m3の熱量は1,280,500kcal。
これは灯油に換算すると154Lに相当する(カロリーは8,341kcal/L)。
灯油価格の全国平均(2022年10月〜12月)は112円/Lなので、154Lの場合、17,193円。
結果として、17,193円(灯油)-5,000円(薪)=12,193円が薪を使うことによる原料のコストメリットになる。この差額であれば、小菅の湯のランニングコストはかなり削減出来るが(薪材の安定調達が前提)、加工費が発生するため、その分を差し引く必要がある。(小菅村の場合は、1m3あたりの製造費は3,000円~4,000円)
同時に、木材はカーボンニュートラル(炭素中立)であることから、CO2排出削減も250〜300t-CO2を確保することが可能であり、クレジット化の取り組みも進めている。
ただし、5,000円/m3の買取価格は搬出費を含めると、なかなか厳しいこともあり、価格設定については出荷者(村内山主さん、北都留森林組合)の皆さんと度々協議を行っている。